- 特集
(財)京都産業情報センター設立20周年記念事業
インターネットマルチ会場大会 開催
インターネットとコミュニティ
京都大学大学院 情報学研究科 社会情報学専攻 教授
石田 亨 先生 |
 |
◎日本人は情報化に消極的?
- インターネットをはじめ世界規模で情報流通革命が進行しています。しかし、これほど急速に情報化が進展しているにもかかわらず、一般市民のインターネットへの関心、信頼感はまだまだ低いというのが実情のようです。
例えば今年2月、新聞各紙にある大手シンクタンクが実施した情報社会に関する国民の意識調査の結果が報道されました。「今後ますます人々のつき合いや、コミュニケーションが活発になると思いますか」という問いに対し、なんと56%の人が「そうは思わない」と答えたそうです。同じ調査を海外でも行ったところ、「そうは思わない」という回答は米国で26%、韓国25%、シンガポールでは10%にすぎません。否定的な回答が過半数だったのは日本だけで、ある新聞は“日本人は情報化に消極的”とショッキングな見出しをつけたほどです。
また、今年6月に私どもの大学の社会情報学専攻の大学院生が、日本、米国、ヨーロッパ、アジアの大学生が発信しているホームページを比較調査してみました。その結果、自分の研究テーマをホームページでアピールしていた博士課程の学生は米国が7割、ヨーロッパでは8割、アジアでも5〜6割もいたのに対し、日本はわずか2割程度。インターネットを使って自分をアピールしようという意欲が他の所と比べて随分と低かったようです。また、教授、助教授などの研究者のホームページを調べてみると、学歴紹介で出身大学や大学院のみを記していた人が欧米、アジアでは8割を占めましたが、日本では全体の6割が高校以前の履歴も紹介し、3割の人が小学校卒業から書いていたそうです。
こうした結果をどう理解すればよいでしょうか。少なくともインターネットを使って個人としてのアイデンティティーを表現する方法が、日本人は各国とは少し違っているのかもしれません。
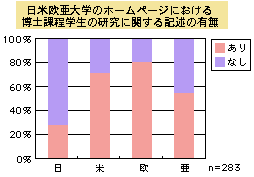
- ◎世界のインターネット利用
- ある統計情報によりますと、パソコンの出荷台数は1993年位まではおよそ横ばい状態でしたが、インターネットが普及し始めた時期からほんの3、4年の間に急速に伸びています。
その結果、インターネット利用人口は一体どうなったでしょうか。各国のユーザ数をみますと、昨年末時点で米国が断然トップの6,200万人、第2位が日本の884万人、次いで英国、ドイツの順になっています。しかし、これを総人口に占める割合でみると、様子が変わってきます。対人口比で日本が7%であるのに対し, 英国、ドイツはそれぞれ10%、7%でそんなに変わらないのですが、米国は23%、カナダ26%、スウェーデン21%、ノルウェー32%、フィンランド24%と、北米と北欧でインターネットを利用している人の割合が著しく高くなっています。
また、ホストコンピュータの台数を対人口比でみると、フィンランドでは10人に1台の割合でインターネットに接続されたコンピュータが所有されていることになるのに対し、日本では1ケタ少なくて数百人に1台の割合です。この差は単に台数の問題ではなく、結果としてのインターネットの利用の仕方が大きく異なってきます。総人口の7%という利用率では、コミュニティにおけるインターネットの利用を考えるのは無理がありますが、30%近い利用率となると断然現実味があって、医療や福祉などへの様々な応用の可能性が出てくる訳です。
次に、日本におけるインターネットユーザの「7%」の中身をみると、男性が83%を占め、うち20代が30%、30代42%、職業は会社員が大半ということで、インターネットの利用は“20〜30代の技術に明るいサラリーマン”が中心であり、市民生活に与える影響は限られたものになっているといえます。これと非常によく似ていたのが1994年の米国における状況で、高収入高学歴の白人男性がインターネット利用者の大半を占めていました。しかし、コスト上の障壁が徐々に取り払われていった結果、利用者の層が大きく広がっていったのです。
そして今、コンピュータネットワークの広域化に伴い、ビジネスからコミュニティとしての利用へと、インターネットをめぐる環境に大きなパラダイムシフトが始まろうとしています。広範囲なインターネットの応用にはやはり利用者人口の増大が不可欠ですので、日本でも現状の7%を30%に持っていけるよう意識的に取り組むべきなのかもしれません。
米国カーネギーメロン大学では一般家庭にコンピュータを貸し出し、インターネットに接続して使い方を指導したり、フィンランドでは高血圧に悩む方々のコミュニティの場としてインターネットの利用が検討されています。日本もやがて同じ方向に向かうのか、あるいは日本独自の利用方法があるのか、普及のシナリオを考えていく必要があるように思います。
- ◎「コミュニティ・コンピューティング」への取り組み
- 1950年代になされたコミュニティという言葉の定義は「不特定多数の人々が生活関心を同時に充足させる場」でした。その成立要因には地域性、社会的相互作用、共通の絆といったものがあり、我々意識、役割意識、依存意識といったコミュニティ感情が重要な要素とされています。つまり、1つの目的や契約によって結ばれている会社などの組織(アソシエーション)とは違って、感性的なものによって成立している部分が大きいといえます。
それでは、どうしてこれがコンピュータの利用について研究する上でのテーマとなってきたか。その背景には、情報工学の分野における大きなパラダイムシフトがあります。
かつてパソコンが出始めた頃は、人間と計算機のインターフェースが主な研究テーマでしたが、企業内ネットワークが導入されると「チーム」が重要なキーワードになり、人間の共同作業を支援するグループウェアや、分散協調システムなどのソフトウェアの研究が盛んに行われました。ところが、約5年前からインターネットが急速に普及し始めて市民生活レベルで利用されるようになったため、さらに多くの人々を含んだ広範囲な領域を示すパラダイムとして「マーケット」、あるいは「コミュニティ」が研究され始めました。
ご存じのように、チームには共通の目的があります。一方、マーケットは目的の違う経済主体の競争を通じて秩序が形成されます。ところが、コミュニティには共通の目的もありませんし、競争による秩序が形成されるわけでもありません。身近な人々の間の協力の関係、共生の関係が広がることによって自己組織的にできていくものです。
私どもが取り組んでいる「コミュニティ・コンピューティング」の目的は、このようなコミュニティの働きをコンピュータネットワークで支援することです。不特定多数の人々の「出会い」「語らい」「集い」に必要な舞台設定あるいは道具立てとして、三次元の仮想空間での出会いを実現する「FreeWalk」を開発したり、100台の携帯端末を用いて「けいはんなプラザ」で開かれた国際会議を支援する「Mobile Assistant Project」を奈良先端科学技術大学院大学やNTTと共同で実施したりしてきました。
その他、仮想空間で知り合い、知識を共有し、コンセンサスを形成し、日常生活を支援する様々な技術開発や社会実験を進めてきました。しかし、こうしたコミュニティ・コンピューティングが有用なものとなるためには、インターネットを通じた社会的なインタラクションが盛んになることが前提になります。そこで、今後の進め方を考えるために、今年6月には内外の社会科学者、計算機科学者を集め、「社会的インタラクションとコミュニティウェア京都会議」を開催しました。
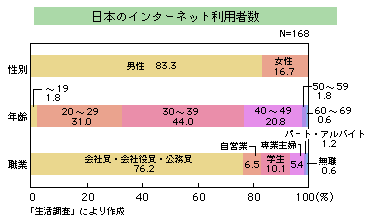
- ◎「デジタルシティ」をめざして
- こうした活動をさらに押し進めていく方向の1つとして、私たちは新しい社会情報基盤としての「デジタルシティ」の形成に取り組み始めています。これは、都市のあらゆるデジタル情報を統合して発信するテクノロジー、コンテンツの総称です。ネットワーク上に構築される架空の都市ではなく、現存する都市(フィジカルシティ)を補完するためのリアリティある都市を指しています。
デジタルシティには、Webに入っているものから街のセンサ情報まで都市のあらゆる情報が収集され、リアルタイムで表示されます。市民は三次元表現されたデジタルシティにアクセスすることによって、交通渋滞、天候の状況から、駐車場の混み具合、商店街の情報などを知ることができます。
現在、ニューヨーク、ロサンゼルスをはじめとして北米や北欧を中心とした各国の主要都市でデジタルシティの開発が始まっており、現実の都市を支えるもう1つの都市として存在しています。中でもよく知られているオランダの首都アムステルダムのデジタルシティの場合、テーマ別に設けられた30以上の街区の内外にバーチャルオフィスや市民の家があり、登録されている“市民”は現在8万人。管理しているのは非営利企業で、25名の従業員が運営にあたっています。
私たちは京都にもこうしたデジタルシティを構築し、京都の豊かな街を再現することをご提案します。伝統芸能や世界文化遺産をはじめとする素晴らしいコンテンツをさらに生かしていこうということです。これは決して“架空”の都市ではありません。将来の都市は、私たちが実際に住むフィジカルな都市と、ネットワークの中に再現されたデジタルな都市によって構成されるようになるでしょう。デジタルシティは常に最新情報を反映した生きた都市であり、防災、物流、交通、商取引、福祉など市民生活を支援する社会インフラといっても過言ではありません。
デジタルシティの実現のためには計算機科学、社会科学、人文科学の共同研究や産官学、自治体の協力などが必要です。様々な連携の機会を活用しながら、新しいインターネットの利用方法として、社会情報基盤としてのデジタルシティを実現していけたらと考えています。
|

