- 特集
いよいよ本番世界標準(グローバル・スタンダード)の時代
- 企業経営のさまざまな局面で「グローバル・スタンダード」(世界標準)への適応が重視される傾向が強まりつつある。世界標準とは、産業技術から会計基準に至るまで幅広い分野で世界共通のルールをつくり、それらの枠内で経済活動をしていこうというもの。大競争時代に勝ち抜くには、もはや日本だけの技術、日本だけのルールは通用しない。産業、企業の競争力を高めるには、世界標準化を視野に入れた経営戦略が欠かせないといえる。
- ■過熱化する標準化競争
- 今日、「国内向け」だけでは通用しないことは、技術開発をみるとよくわかる。すでにコンピュータや情報通信の分野では事実上国境がなくなっているし、日本でしか通用しない技術ではメジャープレイヤーにはなれない。インターネットがオープンな技術だからこそ普及していったのは象徴的な例といえるだろう。
世界標準には大きく2つの形態があリ、競争に勝って市場を制覇したものが標準となる「デファクト・スタンダード」(事実上の標準)と、ISO(国際標準化機構)のような公的機関が定める「デジューレ・スタンダード」(公的標準)とに分けることができる。
デファクト・スタンダードとなるための条件として、技術的に優れていることはもちろん必要だが、いかに技術をオープンにして賛同企業を募るか、また市場を席巻した世界標準のほうにいかに早く適応していくかなどの戦略も重要になりつつある。
AV・家電業界では、日本は古くは家庭用VTRから最近のDVD(デジタル・ビデオ・ディスク)まで輝かしい成果を収めたが、ハイビジョンがデジタル放送に向かう流れのなかで、世界標準に後れをとっている。コンピュータの世界では、マイクロソフト、インテルの圧倒的なシェアに、オラクル、サン・マイクロシステムズ、ネットスケープといったベンチャーが対抗。これらデファクトをめざす戦いに日本企業は全く近づけない状態だ。
携帯電話は、日本は独自規格のため国内だけでしか使えないのに対し、欧州の製品はほぼ全世界で使える。これはGSM(世界移動通信システム)というデジタル通信システムを導入しているためで、もともと欧州のみの統一規格だったが、またたく間に世界へ広がった。欧州勢が携帯電話もまた国際商品であることに着目していた結果といえる。2000年頃に世界市場で実用化が見込まれている次世代機の開発では、日・米・欧の主要通信業者が携帯端末の製品規格を統一することで協議に入り、97年度中にも合意する見通しだ。
一方、品質管理システムの国際規格であるISO9000シリーズや環境管理システムの同14000シリーズ、国際会計基準(IAS)など、デジューレ・スタンダードは、グローバルな立場で事業活動をする際の“パスポート”としての重要度が急速に高まっている。今後は、それらの定める基準を満たしていなければ国際的なプロジェクトに参画できなかったり、海外へ製品を輸出できないという時代がくるかもしれない。
また、モノづくり以外の分野でも、日本は世界標準化の波にさらされている。金融でいえば、預金や保険を集めたりするのはグローバルなオペレーションではないが、為替など金融市場は情報産業的側面が強い。98年4月に外国為替管理法が改正され、為替取引が自由化されると、日本の金融機関が独占権益を持っている1,200兆円もの個人資産に世界の目が集まることが予想される。
電子マネーも金融機関、国際クレジット会社、通信事業者、コンピュータソフト会社などが入り乱れ、標準化競争にしのぎを削っているが、インターネット上で取引ができるようになれば、個人が外国で資産運用するのは簡単になる。そのときは、1980年代に製造業が海外に出ていったように、金融資産が出ていく可能性もある。
ISOとは
スイスのジュネーブに本部を置くNGO(非政府機関)で1947年に設立。100カ国以上が加盟し、日本は理事国の一員でもある。従来は製品の寸法や形などのハードウエアの国際規格を定めるのが主な役割だったが、最近では英国規格をベースに品質管理(9000シリーズ)や環境管理(14000シリーズ)といった全く新しいタイプの規格を定め、将来的には労働安全衛生管理システム(18000シリーズ)も検討課題にのぼっている。本来、法的な拘束力はないものの、グローバル化の進展に伴い企業として対応策が求められている。 |
- ■ISO取得へ企業が意欲
- ◎経営のツールとして−ISO9000シリーズ−
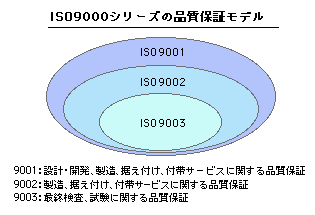 ISO9000シリーズでは、個々の製品の品質をチェックするのではなく、良質な製品を安定して供給できるシステムを企業が構築しているかどうかが問われる。品質管理システムさえできていれば、おのずから不良品は排除され、良品だけが出荷されてくるはず、というのがそもそもの発想だ。
英国の規格をモデルに1987年に制定されたISO9000は、92年のEC市場統合を機に日本でも認証の取得がブームとなった。その後、やや下火になったものの、ここへきて再び認証取得の動きが活発になっている。認証を取得するには、(財)日本適合性認定協会(JAB)が認定した審査登録機関の審査を受けて合格する必要があるが、その後も年に1回以上のサーベイランス(維持審査)や3年以内に1回の更新審査で、合格した水準のレベルを維持しているかがチェックされる。
ISO9000の手法は企業の自主性に任せられ、誰が見てもわかりやすく、明確なものであることが求められている。
そこで重視されるのは、
(1)企業は品質に関してどのような方針を持っているのか
(2)誰がどのような権限や責任を分担しているのか(職務分掌)。組織はどうなっているのか
(3)どの作業をどのような手順でしているか
(4)それらが第三者にわかるように文書化(マニュアル化)されているか
(5)マニュアルどおり実行されていることを証明できる記録があるか
などの点だが、あくまでも不適合品を出さないための規定であり、その意味では消極的なところもある。マニュアル作成にあたってTQCの伝統が根づいている日本では積極的に解釈して項目を付け加えていく企業が多いが、ポイントは「使いやすく、できるだけシンプル」であることだ。
ISO9000が発効された当初、QCサークルを通じて欠陥をひとつひとつ減らしていく日本流の品質管理方法とは異質なことから、「日本の企業風土になじまない」との声もあった。ところが、認証取得を促す“外圧”もあって、欧州生まれの品質管理手法が世界標準として普及し、経営ツール、マネジメント手法として導入する企業が増えてきた。その要因としては、若年労働者の流動化やパートの即戦力化、熟練工の高齢化に伴う技術継承などの課題を解決するために、製造現場では作業手順の文書化、マニュアル化が求められているということもあげられる。従来のTQCとISOをミックスさせて有効に活用することで、飛躍への道が見えてくるかもしれない。 ISO9000シリーズでは、個々の製品の品質をチェックするのではなく、良質な製品を安定して供給できるシステムを企業が構築しているかどうかが問われる。品質管理システムさえできていれば、おのずから不良品は排除され、良品だけが出荷されてくるはず、というのがそもそもの発想だ。
英国の規格をモデルに1987年に制定されたISO9000は、92年のEC市場統合を機に日本でも認証の取得がブームとなった。その後、やや下火になったものの、ここへきて再び認証取得の動きが活発になっている。認証を取得するには、(財)日本適合性認定協会(JAB)が認定した審査登録機関の審査を受けて合格する必要があるが、その後も年に1回以上のサーベイランス(維持審査)や3年以内に1回の更新審査で、合格した水準のレベルを維持しているかがチェックされる。
ISO9000の手法は企業の自主性に任せられ、誰が見てもわかりやすく、明確なものであることが求められている。
そこで重視されるのは、
(1)企業は品質に関してどのような方針を持っているのか
(2)誰がどのような権限や責任を分担しているのか(職務分掌)。組織はどうなっているのか
(3)どの作業をどのような手順でしているか
(4)それらが第三者にわかるように文書化(マニュアル化)されているか
(5)マニュアルどおり実行されていることを証明できる記録があるか
などの点だが、あくまでも不適合品を出さないための規定であり、その意味では消極的なところもある。マニュアル作成にあたってTQCの伝統が根づいている日本では積極的に解釈して項目を付け加えていく企業が多いが、ポイントは「使いやすく、できるだけシンプル」であることだ。
ISO9000が発効された当初、QCサークルを通じて欠陥をひとつひとつ減らしていく日本流の品質管理方法とは異質なことから、「日本の企業風土になじまない」との声もあった。ところが、認証取得を促す“外圧”もあって、欧州生まれの品質管理手法が世界標準として普及し、経営ツール、マネジメント手法として導入する企業が増えてきた。その要因としては、若年労働者の流動化やパートの即戦力化、熟練工の高齢化に伴う技術継承などの課題を解決するために、製造現場では作業手順の文書化、マニュアル化が求められているということもあげられる。従来のTQCとISOをミックスさせて有効に活用することで、飛躍への道が見えてくるかもしれない。
国際会計基準(IAS)
投資家や取引先は企業の決算書などを見て評価・分析するが、そのモトになるのが会計基準。国際会計基準委員会(IASC)では1998年3月の完成を目標に作成を進めており、2001年3月期から国際資本市場での運用が行われる予定。
日本方式と最も異なるものをあげれば2点ある。1つは資産価値の評価方法で、日本の取得した原価での簿価会計主義に対し、IASでは時価会計主義に変更される。つまり、貸借対照表の数字がすべて現在価値に変わる。2点目は情報の開示方式。これまで財務諸表は単独決算が主で、連結決算は従という感覚だったが、IASでは連結決算中心へ移行し、日本方式とは逆転する。連結中心の決算になれば、子会社を使った会計操作ができなくなり、本体だけでなく企業グループ全体の収益力が問われることになる。 |
MONTHLY JOHO-KYOTO

|

