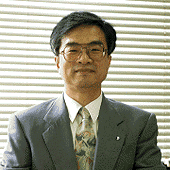情報化をどう進めるか ――星和電機(株)から分社されて3年。一昨年には京都リサーチパーク内に開発センターを開設されましたね。 荒木 現在はこのセンターをTSC(Techno Symbiotic Center)と呼んでいます。Symbioticは「共生」、技術を通してお客様とともに共生の道を見いだしていきましょう、というのがコンセプトです。  ――この間、事業のスタンスに何か変化はありましたか。 ――この間、事業のスタンスに何か変化はありましたか。荒木 当初は試行錯誤の連続で、コンピュータ機器を売ったり、ネットワークのケーブルをつくったりもしましたが、実はニーズはそんなところにあるのではない。お客様が望んでおられるのは、情報化といってもどうすればいいのかわからない、その取り組み方、進め方を教えてほしい、ということに気づいたんです。 また、中堅・中小企業をターゲットに考えていたのですが、この頃は大企業からも声をかけていただくようになりました。「なぜ我々のような知名度もない会社に依頼されるのですか」と尋ねたところ、「情報化をどう進めていくか、親身になって相談に乗ってもらえるところがない」と。そこで、コンサルティングをさせていただけるのなら、一緒にシステムを構築いたしましょうというスタンスに変えました。 ――初めにコンサルテーションありき、というわけですね。 荒木 SI(システム・インテグレーション)のベンダーさんはたくさんおられますが、通常、こんなサーバーを置いて、それからこういうシステムを使って……と提案されることが多いですね。その結果、おカネをかけたけれども誰も使わない、使えないといったケースも起きています。口はばったいですが、お客様が新たに機器を買いたいとおっしゃられても、その段階ではないと思ったら「いまは買うべきではありません」とあえて申し上げています。 もし東京でやっていたら、あるいはモノ(機器)が売れればいいという考え方に立っていたかもしれません。市場は京都の10倍が大阪、東京は大阪のさらに10倍と巨大ですから。しかし我々は、モノやシステムを売るのではなく、情報化をいかに効率よく進めるかがテーマなんです。これまで業界内はメーカー系とシステムハウスの二極構造になっていて、その間を埋めるものがない。我々はその橋渡し役でありたいと考えています。ソフトは開発するけれども、システムハウスとしてビジネスをしていくつもりはありません。 “一緒にやりましょう” ――そうした独自のスタンスが他社との違いでもあるわけですが、具体的にはどのようにしてコンサルティングされるのですか。 荒木 情報化推進のトップの方に必ず入っていただくことにしています。もちろん技術面のキーマンの方とも話をします。「カネを出すからとにかくやってくれ」という経営者がよくおられますが、そういう場合は大体うまくいきません。“一緒にやりましょう”ということでご理解いただけないと、基本的にはお引き受けしないことにしています。最近は業界大手の企業もコンサルティングから入る手法をとり始めたので、我々だけが特殊ということではなくなってきた半面、お客様の理解は得られやすくなりました。 情報化というのは本来ツールにすぎません。お客様が目標をどう実現するか、そのための情報化を推進するにあたっては問題点を抽出することが大事です。我々は以前からマルチベンダーのシステムに取り組んできましたから、どこに問題があるかはすぐわかります。例えば、メモリーがどれだけ有効に使われているかというチェックシステムも開発しました。 ――売り上げも順調に推移していますね。 荒木 たしかに売上高は伸びていますが、親会社からのアウトソーシングが50%を超えています。お互いに甘えをなくし、緊張感を維持するためにも“依存率”を下げることが当面の課題です。 ――今後の方向性についてはどのようにお考えですか。 荒木 いまのビジネススタイルは当分続けるつもりです。そして「いいものができてよかった」とお客様に喜んでいただくことが、我々にとって最大の報酬です。それには絶えず自己研鑽を積んでいかなくてはなりません。この事業を始めて痛感したのは、技術革新のテンポがあまりにも速すぎること。それについていくには四六時中、情報をフィルタリングしていく必要がある。社員が現在13人ですから大変ですが、常に最新の技術にふれるチャンスにもなり、社内の活性化にもつながっています。将来的には会社自体をそんなに大きくするつもりはありません。経営トップが1人で管理できる規模はせいぜい50人程度まででしょう。事業分野が拡大していけば分社化する方針です。 産学連携も将来視野に  ――異業種交流や産学連携の活動についてはいかがですか。 ――異業種交流や産学連携の活動についてはいかがですか。荒木 できる限りいろんな方々とおつき合いさせていただくようにしており、交流の場がきっかけになって産官学共同の調査事業にも参加いたしました。産学連携については独自にやってみたいのですが、まだまだ社内の体制ができていません。情報化推進は経営・経済学の面からも重視されてきていますので、文系の学生にも実際に体験してもらおうと大学にサーバーを無償でお貸しする形で協力させていただいています。 ――会社と社員がネットワークで結ばれ、SOHOの環境にもなっているとか。 荒木 会社−社員宅はすべてISDNを通じてアクセスできるなど在宅勤務の環境を整え、本人がのぞめばフレックスタイムも認めています。それと併せて、給与面も年間最大4回まで見直すことができる仕組みにしています。成果によって上がりもするし、下がることだってある。こちらも3カ月ごとというのは大変なんですが、下がった人は3カ月後にはまた上がるチャンスがあるわけです。そうして自分自身の価値を高め、個人の力でも仕事ができる人間に育ってもらいたいと考えています。
MONTHLY JOHO KYOTO 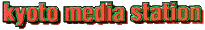 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||