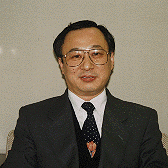「10年早い」大いに結構 ――昭和56年に社員わずか2名でスタートされ、飛躍的な発展を遂げられましたが、その原動力は? 藤関 いうまでもなくコンピュータソフトの世界は、企業にとってひとが財産のすべてです。創業当初から“ひとはじめにありき、ひとはちから、ひとはたから”を経営理念に実力主義で臨んできました。私で3代目なんですが、前任の2代目社長の時、店頭公開をめざして従業員500人体制を目標に掲げました。業界自体が急成長産業としてもてはやされていた頃です。ところがバブル経済の崩壊とともに成長神話は崩れ、厳しい企業経営を強いられた時期もありました。 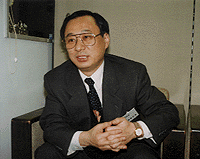 ――社内体制の現況はどうなっていますか。 ――社内体制の現況はどうなっていますか。藤関 一時は従業員200人を数えましたが、今3月期末では77名、うち70名が技術者です。間接部門以外は全員が技術者で、SEすなわち営業マンというわけです。我々はモノをつくっているのではない。ユーザーのためにどんなソフトを提供できるかが営業の第一歩ですから。 ――そこで個人の可能性を引き出す人材育成の秘訣みたいなものはありますか。 藤関 以前は中途採用をしていましたが、それではどうも他力本願みたいなところがある。やはり自前でユニシスならではの人材を育てていこうということで、近年は新卒採用に力を入れています。例えば、入社早々の社員が何か意見をいうと、先輩社員がよく「それをいうのは10年早い」とたしなめることがありますね。むしろ若い人たちの感性でどんどん問題を投げかけてもらってこそ、会社自体の底上げにつながると思っています。ですから、若い社員には「存在感のある人間になってほしい」と。自分たちがやりたいことを会社に対して仕掛けなさい、やりたいと思えば“できる、できない”は超えられる。10年早くても大いに結構、その中からいいものを会社が吸い上げていけばいいんです。 ――会社の明日をつくる新人の採用にあたっては何を重視しておられるのですか 藤関 関西を中心に大学4回生にDMを出し、何度も会社説明会を開いています。特殊な専門能力が要求される分野以外は文系、理系を問いません。要は物事に対する取り組み姿勢です。会社が何をしてくれるのかではなく、自分は会社で何をするのか、何をしたいのか。それを自ら探し出してアピールしてほしいですね。今春は9名採用しました。 年功3:能力7 ――ユーザーの業種、開発ソフトのジャンルは? 藤関 金融機関からメーカー、官公庁、学校関係と対象は幅広く、自動改札の制御や生産管理システム、通信ネットワーク、基本ソフトなど多様なジャンルを手がけてきました。京都地区では創業以来お付き合いさせていただいている大手ユーザーもあり、技術者の評価と同時に信頼関係というつながりでやらせていただいています。 ――業界はいま、「2000年問題」で活況を呈しているとか。 藤関 2000年問題の対応サービスということで特別な取り組みはしていません。誤解を恐れずにいえば、“後ろ向き”の業務という感がありますし、この時期だけの仕事だからです。その間にも情報サービスの世界は日進月歩ですから、技術力の低下のほうが心配です。ただ、これを機会に全面的にシステムを見直したいというニーズには対応しています。 ――受注したシステム開発はどのようにして進められるのですか。 藤関 受注内容にもよりますが、標準パターンですと10人程度でプロジェクトチームを組み、リーダーが進捗状況、品質、納期の管理をします。そしてお互いにディスカッションしながら作業を進めていきます。今日ではプログラミングはできて当たり前、制御系をはじめ高度なスキルが要求されてきているのが現状です。コンピュータを通して社会の先端をいく仕事ですから、システムアナリストとして世の中を鋭く見つめる目を持たなければなりません。したがって人事の評価基準は「年功3:能力7」。能力には性別も学歴も年令も一切関係ありません。 ――そのためには自由な環境づくりが必要ですね。ところで社員の平均年齢は何歳ですか。 藤関 かつては完全フレックスタイムでしたが、いまは10:00〜16:00のコアタイムを設けています。平均年齢は32.7歳で、男子が34歳、女子は29.8歳。育児休業を取得している女子が現在3名おり、身につけた技術をできるだけ生かしてもらいたいというのが方針です。 ユーザー提案型めざして 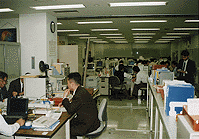 ――実力派のソフト開発集団として、これからの戦略的方向づけは? ――実力派のソフト開発集団として、これからの戦略的方向づけは?
藤関 業界を見渡すと3つの形態があります。まず請負型、それから一歩踏み込んだユーザー提案型、そしてジャストシステムに代表されるような自社ブランドを持つ企業です。現状は請負型が大半を占め、当社もその域からまだまだ脱皮しているとはいえません。ユーザーが抱える問題を一緒に考え、改善提案をするコンサルティング機能の発揮も、付加価値を高める事業として視野に入れていきたいと考えています。 ――社長の考える請負型からの脱却策のポイントは何ですか。 藤関 委託業務の内容が複雑・高度化していることやダウンサイジング化、オープン化といった環境変化への対応については、特定の専門技術や知識だけで対応できるものではなく、複合的な技術や知識の集積が必要です。つまり、個人的技量での対応には限界があり、組織的対応がどうしても欠かせません。したがって、社内の上から下まで、下から上まで情報の共有化と、これからもやはり多様な人材の確保と育成がベースになると思います。 企業の健全な発展の第一歩は量より質、質を伴ってこそ真の拡大につながる、というのがバブル期の苦い体験から得た実感です。質の追求へ努力を積み重ねていけば、数字はおのずからついてくるのではないでしょうか。
MONTHLY JOHO KYOTO 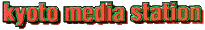 | ||||||||||||||||||||||