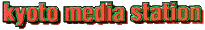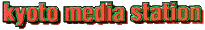京都・人・産業
巻頭インタビュー Vol.1
京都学園大学
波多野 進 教授
- 設問1-
情報技術の劇的な進歩を京都の中小企業はどのように受けとめるべきか。また、その活用については。
 それぞれの企業の技術は進歩しているが、情報マインドとなるとさほど進歩していない。
1つは、それらを取り巻く社会環境が問題。京都には情報化に対するシーズが山ほどある。文化、学術はもちろん町そのものが情報であることはいうまでもない。しかしそれを具体化していこうというパワーに欠ける。つまり、京都人は情報技術に対して前向きでなく、情報に対するオープンなマインドに欠けている。京都の情報シーズを活用しようするならば、もう少し自由に流通できる環境でなければいけないし、また地域全体が情報マインドに対してオープンでなければ活力のある社会はできない。 それぞれの企業の技術は進歩しているが、情報マインドとなるとさほど進歩していない。
1つは、それらを取り巻く社会環境が問題。京都には情報化に対するシーズが山ほどある。文化、学術はもちろん町そのものが情報であることはいうまでもない。しかしそれを具体化していこうというパワーに欠ける。つまり、京都人は情報技術に対して前向きでなく、情報に対するオープンなマインドに欠けている。京都の情報シーズを活用しようするならば、もう少し自由に流通できる環境でなければいけないし、また地域全体が情報マインドに対してオープンでなければ活力のある社会はできない。
2つ目は、京都の企業は新技術への対応が遅いということ。京都はベンチャー企業の集積のように言われているが、実は海外や学術機関などのセカンドソースの情報で発展した企業がほとんど。まったくの新開発技術によって成長したのではなく、京都のベンチャー企業の真骨頂は製造技術だ。そうした中、現在の企業に必要なのは経営の感性を磨くことだ。真のオリジナルに対応する起業家育成には、外部からの新しい人材が必要。しかし新しい人材が入ってきて自由に活動する場としては、京都はあまりにも排他的で相応しくない。情報技術の進むなかで、現在の中小企業に求められているのは、おおいに世界へ出て、各国の新しい技術をもった人材と交流し、自社の技術を発展させること。京都の中だけで動くのではなく、世界的規模で考え自由に飛び回ることが必要だ。
そして3つ目は、京都のシーズをうまく活用する技術を高め、コンテンツへのアクセスを意欲的に行うこと。京都で情報技術を発展させるための焦点は、コンテンツ。コンテンツを数多いシーズにどうのせていくか、そしてそのメリットを考えるべきだ。日本でコンテンツを求めようという意欲のある企業はこれからどんどん京都へやってくる。そうした大手企業をうまく利用して経営に結び付けることも可能。そういうコンテンツを満たすアクセスを積極的に進めてみよう。
京都の情報産業発展には、世界中の大手ネットワーカーとアクセスして活動する各中小企業の活躍が欠かせない。
(続く)※シリーズ4回で掲載する予定です
MONTHLY JOHO KYOTO
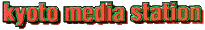
|